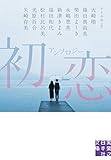ドミノ in 上海 [読書・その他]
評価:★★★☆
高価な "お宝" が上海へと密輸されたが、ある手違いから "お宝" は別の場所に届いてしまい、地下組織の一味は必死にその行方を追う。
それに東京から来たOL、寿司デリバリーを営む日本人夫婦、映画撮影にアメリカからから訪れた制作陣一行、上海警察署長たちが巻き込まれ、さらには動物園を脱走したパンダまでが "参戦" して、"お宝" をめぐる大騒動が上海の夜を駆け巡る・・・
『蝙蝠』(こうもり)というコードネームで呼ばれる "お宝" が、闇ルートを通じて上海に持ち込まれた。輸入される動物の胃の中に隠すといういつもの方法だったが、今回は輸送中に予想外の "手入れ" が入り、とっさに近くの檻の中にいたイグアナに飲ませてしまった。
そのイグアナは、アメリカ人映画監督のペットで、上海での映画撮影に同行させようとしていたもの。彼の宿泊していたホテル・青龍飯店に届けられたが、檻から逃げ出して厨房に入り込み、それを新たな食材(笑)と勘違いしたコックによって "調理" されてしまったのだった(おいおい)・・・
中国の人は、足が四つあればテーブル以外は何でも食べるっていう話を聞くけど、ホントのところはどうなんだろう。
地下組織は『蝙蝠』の行方を血眼になって探し始めるが、その動向を香港警察の潜入捜査官たちも追っていた。
そして "お宝" のことなど全く知らない一般人たちも、その騒ぎに巻き込まれていく。
東京からやってきたOL二人組が訪ねたのは、上海で寿司デリバリーを営む日本人夫婦。二人の店は迅速な配達がウリで、スピード制限など無視してオートバイでかっとぶ。それを目の敵にするのが、マスコミ受けを気にする上海警察の新署長だ。
最愛のペットを喪い、意気消沈した監督にやきもきする助監督、プロデューサー、配給会社の日本人スタッフたち。
そこに現れた風水師は、なんとダリオの霊が "見える" ようだ。と思ったら、日本人スタッフの女性は神社の宮司の娘で、こちらも "見える" みたいだ(なんと!)。
青龍飯店の最上階ギャラリーでは美術品の展覧会が催され、そこでは商談も交わされる。今回の目玉作品を出品する現代美術家は、実は借金で首が回らない。彼はこの展覧会に於いて、ある "企み" を実行しようとしていた。
そして人間以外も "参戦" する。上海動物公園のジャイアントパンダ・厳厳(グヮングヮン)。過去にも逃げ出したことがあり、飼育員から目をつけられているが、本人(?)は再びの脱走を狙って虎視眈々と機会をうかがっており、ついに決行の時を迎える。
厳厳のパートは本人(?)のモノローグの形で綴られる。このパンダは実に明晰な頭脳を持っており、自分の置かれた状況の把握も完璧で、そこから綿密な脱走計画を組み立てていく。
このあたり、パンダを人間に置き換えれば、そのまんま囚人が脱獄を狙う話に読み替えられるのが笑える。
とまあいろいろなキャラを紹介してきたが、ひとたび本を開くと、彼ら彼女らのストーリーが同時進行的に、あるときは単独で、あるときは他のストーリーラインに絡みあい、ドタバタ騒ぎが始まっていく。それはどんどんスケールアップしていき、事態は混迷の度を深めていく・・・
本書の冒頭には「登場人物よりひと言」という、各キャラの紹介ページがあるのだが、そこに挙がっているだけで25人+3匹(笑)もいる。
あまりに多すぎて覚えきれない人は、この紹介ページは重宝するだろう(私がそうでした)。
2001年刊行の『ドミノ』の、いわば続編なのだけど、ストーリーは本書のみで独立している。前作と共通する登場人物もいるけど、前作を知らなければ困ることは何もない。
何より、前作を読んでいたけど、内容をさっぱり忘れていた私でも充分楽しめたのだから、間違いない(おいおい)。
第四の暴力 [読書・その他]
評価:★★☆
立法・司法・行政と並んで、「第四の権力」と云われるマスメディア。大衆に対して大量の情報を迅速に伝える媒体として重要な地位にありながら、時にその権力の大きさから、暴走とも云える行為に走ることもしばしば。本書は、そんなマスメディアの "暴力" を描いた短編三作を収める。
「生存者一名あるいは神の手(ラ・マーノ・デ・ディオス)」
とある山村を豪雨が襲い、発生した土石流によって村は全滅してしまう。樫原悠輔(かしはら・ゆうすけ)は、たまたま叔父のところに金策に出かけていて惨禍を免れ、ただ1人の生き残りとなってしまう。
村へ帰った悠輔は、その惨状に呆然とする。妻と2人の子は膨大な土砂の下に生き埋めになっており、生存は絶望的。そんな彼にさらなる追い打ちがかかる。現地へ押しかけてきたマスコミから追い回される羽目になったのだ・・・。
いわゆる暴走するマスコミの "餌食" となってしまった男の悲劇、そしてそれに対して蓄積していく鬱憤、そして爆発(!)が描かれていく。
終盤の展開は・・・これは読んでのお楽しみか。
そして、物語の結末は「読者に選ばせる」という驚きの仕掛け。その選択によって、続く2つの話のどちらかへ進む、という流れになってる。
「女抛春(ジョホールバル)の歓喜」
主人公の子安(こやす)は、某キー局でバラエティ担当のプロデューサー兼ディレクター。その権限は絶大で、番組内ではまさに独裁者。ADたちを奴隷のように酷使する日々。
ところがある日、収録中に身体に異常を覚え、救急車で病院へかつぎ込まれる。検査結果を待つ間、彼は可愛い看護師相手に昔話を始める。
過去の担当番組で "演出" という名の〈やらせ〉をしたこと、集まらない参加者の枠をADで埋めたこと、彼らに課されるのは拷問と見紛うばかりの無茶振り、罰ゲーム的な仕打ちだったこと・・・これは今でもバラエティ番組でお笑い芸人が同じことをやってるが(笑)。
そして判明する子安の病状と、それに対する彼の反応。いやはや、ここまでくればいっそ天晴れか。
「童波(ドーハ)の悲劇」
主人公の津島はエリートサラリーマン。同僚たちが芸能人関係の話題で盛り上がっているのを内心では軽蔑している。そんな津島は、社内で行われる超エリート養成研修に選ばれる。一年間にわたって最先端技術の講習、12カ国語に渡る語学研修、世界中の支社の視察を行うなどの超英才教育を受けるものだ。津島は恋人の琴音にしばしの別れを告げ、勇躍して海外へと出発するのだが・・・
マスコミの暴走が極まった世界が描かれるのだが、これが絵空事で終わることを願ってしまう。
「手のひらを返す」って言葉があるが、「マスコミの手のひらは返すためにある」といつも思ってしまう。
調子の良いときは "褒め殺し" と見紛うばかりに徹底的に褒め倒し、いったん落ち目になったら "水に落ちた犬は叩け" とばかりに圧倒的な集中砲火。
具体例は挙げないけど、最近のニュースを見ていても感じることがあるのではないか。このようなマスコミの姿勢はここ何十年もの間、一向に変わっていないように思う。
「(対象が)プロアスリートや芸能人なら、そんなふうに扱われるのも当たり前で、仕方のないことだろう」って考える人もいるかもしれない。でも、あまりにも臆面が無さ過ぎるように思うんだが。
火のないところに煙は [読書・その他]
評価:★★☆
「神楽坂を舞台に怪談を」との依頼を受けた作家の〈私〉。かつて体験したことを題材に、短編1作のみで終わるはずが、次から次へと怪異が続き、続編を執筆することに・・・
ドキュメンタリー形式で語られるミステリアスな怪談。
「第一話 染み」
「怪談」をテーマに、『小説新潮』から短編小説の依頼を受けた "私" は、過去の体験をもとに小説化することに。
8年前、"私" は友人の瀬戸早樹子(せと・さきこ)の紹介で角田尚子(つのだ・なおこ)という女性と会った。
尚子は結婚を考える男性がいて、『神楽坂の母』と呼ばれる評判の占い師を訪ねたところ、「不幸になる」「結婚しない方がいい」と断言されてしまった。
しかし相手の男性は別れ話に対して怒り出し「別れるなら死んでやる」と言い出した。男の行動は次第にエスカレートするが、ある夜、交通事故で死亡してしまう。
"私" から相談を受けたオカルトライターの榊桔平(さかき・きっぺい)は、死亡事故の状況から、ある推理を組み立てるのだが・・・
作中に登場する、ある "アイテム" が実に怖い。それが文庫本の裏表紙にも載ってるので二度びっくり。
「第二話 お祓いを頼む女」
フリーライターの鍵和田君子(かぎわだ・きみこ)のもとに、ある日突然、平田千恵美(ひらた・ちえみ)という女性から電話がかかってくる。お祓いをお願いしたいという。「私、祟られているんです」
夫は交通事故に遭い、息子も様子がおかしいという。
お祓いはできないというと、できる人を紹介しろという。どう話しても会話がかみ合わない。なんとか電話を切るがその数時間後、こんどは本人が君子の家に現れる。
君子から話を聞いた榊は、ある推理を提示する。それですべて解決かと思われたのだが・・・
ミステリ的な解決がなされたと思ったら、さらに(ホラー的に)ひとひねり。
「第三話 妄言」
新婚の塩谷崇史(しおや・たかふみ)は埼玉県の郊外に家を買った。条件のよい物件で喜ぶが、ある夜、帰宅した彼を妻は詰問する。隣家の主婦である前原寿子が、崇史の浮気現場を目撃したというのだ。
寿子の処へ抗議に向かうが、彼女は「絶対に間違いない」との一点張り。どうやら彼女は、そのように "信じ込んでいる" らしい。
「とんでもないところへ家を買ってしまった・・・」後悔する崇史だが、妻は次第に寿子に感化されていってしまう・・・
このあと悲惨な出来事が起こり、それを取材した榊によって、寿子がとった行動の "理由" が推測されるのだが・・・。こんな "迷惑な隣人" がホントにいたら恐怖そのものだなぁ。
「第四話 助けてって言ったのに」
ネイルサロンで働く智世(ともよ)は、夫・和典の実家で義母・静子と同居していた。姑との仲は良好だったが、同居を始めた頃から奇妙な悪夢を見るようになった。
家が火事になり、炎と煙に追われて焼け死ぬというものだ。それを聞いた和典は驚く。それと全く同じ悪夢を、かつて静子も見ていたのだという。
悪夢の原因が住んでいる家にあるのではないかと考えた和典は、家を売りに出す。幸い、買い手がついたのだが・・・
榊の推理は、関係者の "善意"(悪意ではない)を明らかにするが、善意が必ずしも人を救わないという哀しい話。
「第五話 誰かの怪異」
千葉県内の大学に入学した岩永幹男(いわなが・みきお)は、格安の古アパートで一人暮らしを始めた。しかし、やがて怪異に見舞われるようになった。
風呂場の排水溝に大量の毛髪(明らかに自分のものではない)が詰まっていたり、突然TVのチャンネルが切り替わったり、洗面所の鏡の中に見知らぬ高校生くらいの少女が映っていたり。仲介の不動産屋に問い合わせたところ、過去にアパートの隣室で4歳の少女が亡くなっているという。
友人に怪異を話したところ、"霊が見える" という男・岸根を紹介される。アパートにやってきた岸根は、「ここには霊がたまりやすくなっている」というのだが・・・
このあと物語は二転三転して、明らかになるのは死者ではなく、生者の悲しみ。
「最終話 禁忌」
五話目まで書き終わった "私" は、まとめた原稿を榊に送る。彼に書評を書いてもらうためだったが、彼と話をしているうちに、"私" は5つの話に意外なつながりがあることに気づくのだった・・・
巻末には、"榊桔平が書いた書評" まで載っている。もちろんこれも作品の一部となっており、芸が細かいというか・・・
総じて、どの話も奇怪な事態が発生する。その一部は榊によって解き明かされるのだけど、それでも謎は残り、それによって、より恐怖感が増すという作り。
ミステリ要素とホラー要素の比は 4:6 というところかな。謎が解けても全然安心できないのはイヤだなぁ。やっぱり私はホラーが苦手です。
Another [読書・その他]
主人公・榊原恒一(さかきばら・こういち)は夜見山(よみやま)北中学校3年3組へと転校する。しかしクラスメイトたちは、なぜか一人の女生徒を執拗に無視し続けていた。彼女の名は御崎鳴(みさき・めい)。不思議な存在感をもつ美少女だった。
やがて恒一と鳴は、3年3組に起こる凄惨な事件に巻き込まれていく・・・
1998年4月。父親の海外勤務に伴い、祖父母のいる夜見山市へやってきた榊原恒一。しかし転居早々、肺を患ってしまい、入院することになってしまう。
転校先の夜見山北中学校への登校は退院後、ゴールデンウィーク明けの5月からになった。しかし恒一は転入先の3年3組の雰囲気の異様さに困惑する。
クラスメイトたちは、なぜか女生徒の一人を執拗に無視し続けて("いない者"として扱って)いるのだ。彼女の名は御崎鳴。左目に眼帯をつけた、不思議な存在感をもつ美少女だった。
彼女に惹かれた恒一は、鳴と接触を試みる。口数が少ない彼女ではあったが、次第に会話ができるようになっていく。
そんなとき、クラス委員の桜木ゆかりが事故死する。そしてそれをきっかけに、クラスメイトやその関係者の間で死者が続出し始める。
それは26年前の "ある出来事" がきっかけだった。それ以来、夜見山北中学校3年3組は "死に取り憑かれて" しまった。
何年かごとに、クラスの生徒や親族などの関係者に、死者が大量に発生するという "災厄" がやってくるのだ。クラスメイトたちが鳴を "いない者" として扱っていたのも、これに関わりがあった。
恒一と鳴は、"災厄" の謎を探り始める。"死の連鎖" を食い止める方法を探して・・・
作家・綾辻行人の代表作のひとつで、メディアミックスで話題となったホラー・ミステリ。文庫版の初刊が2011年の秋で、その頃に一度読んでいるはずだから、12年ぶりの再読となる。
なんで再読したのかというと、近々『Another 2001』が文庫化されるとアナウンスされたから(実はこの文章を書いてるのが 2023/6/13 で、この日が発売日だ)。
手元にはスピンオフ的な続編『Another エピソードS』(文庫版)があったのだけど、これを買ったときには『Another 2001』の雑誌連載が始まっていたと記憶してる。
じゃあ『Another 2001』が文庫になったときに一緒に読もうと思って放置しておいたら、連載がなかなか終わらず(それゆえに文庫化もずいぶん後になって)、ここまで来てしまった、というわけだ。
12年ぶりに再読してみて、相変わらず面白いなぁ上手いなぁ、って思った。何より文章が読み易い。とにかくするすると読める。”この内容” をこういうふうに書けるだけで作者は天才だと思う。
その一方で、驚いたのは内容をかなり忘れていたこと。
全体の設定や序盤~中盤のストーリー(文庫で言うと上巻にあたる部分)はかなり覚えてたのだが、下巻に入ってからは、ほとんど記憶にない展開で、初読みたいな感覚を味わったよ。
当然ながらクライマックスの決着も、"オチ" もすっかり忘れていて、もう一度 "驚く" ことができました(おいおい)。
読者としては楽しめて良かったのだけど、自分の記憶力がいかに当てにならないかを痛感して呆然としてしまいました。
宮内悠介リクエスト! 博奕のアンソロジー [読書・その他]
評価:★★☆
「博奕」(ばくち)をテーマにしたアンソロジー。いわゆるギャンブルに限らず、広く "賭け事" を対象にしている。賭けるものも現金に限らず、いろいろだ。
「獅子の町の夜」(梓崎優)
主人公の "僕" はビジネスマン。仕事で訪れたシンガポールで日本人の老夫婦と知り合う。その午後、"僕" は夫人とディナーのデザートを巡って賭けをすることに。結果によっては夫と別れると彼女は云う。
夫人を思いとどまらせるために、"僕" は彼女よりも先にデザートが何なのか突き止めようと推理を巡らす・・・
ホテルのレストランでのディナーなんて、食べたことあったかな? そのせいか、オチの意味が理解できるまで時間がかかった(おいおい)。
「人生ってガチャみたいっすね」(桜庭一樹)
2019年6月。ルームシェアしている3人の若者の会話から始まる。続いて2020年10月のある会社での情景が描かれる。そして改めてこの2つの時間の間に何があったのかが語られていく。それはなかなかショッキング。そしてラストはちょっぴりSFチック。
紹介が難しいのだが、こういう話は嫌いじゃない。
「開城賭博」(山田正紀)
時代は慶応4年(1868年)。官軍が江戸城を包囲し、総攻撃が始まろうとしていた頃。
幕府側の勝海舟が、官軍指揮官・西郷隆盛を相手に、江戸城明け渡しの条件を賭けて博奕の勝負をするという話。
こういうことを思いつくんだねぇ、流石は山田正紀。
「杭に縛られて」(宮内悠介)
1998年。主人公の "わたし" はアフリカのエリトリアにいた。しかし隣国のエチオピアがエリトリアに対して宣戦布告したため、急遽国外への脱出を迫られる。
しかし乗り込んだ貨物船はオンボロの老朽船。紅海へ出港したはいいが、座礁してしまい沈没の危機に。乗員乗客総勢20人に対して、救命ボートは8人乗り。誰がボートに乗るかの "くじ引き" が始まる・・・
深刻な事態なのだが、ユーモラスな語り口で喜劇調で進むのがいい。
「小相撲」(星野智幸)
一時期、大相撲が "八百長" だと騒がれた時期があったが、本作はまさに相撲が "賭博" の対象になっている世界の物語。
さながら競馬のごとく、客は取り組みを選んで賭ける。ただし、その際には相撲賭博師という "プロ" を通さないといけない・・・
設定的には面白いのだけど、相撲協会から訴えられないのかしら?
「それなんこ?」(藤井太洋)
ITエンジニアの "わたし" は、故郷の奄美大島に戻って墓参りをする。そこで出会った少年に、薩摩伝来の賭け事 "ナンコ遊び" にまつわる過去の想い出を語り始める・・・
うーん、作中の "ナンコ遊び必勝法" の理屈が、いまひとつ分かりませんでした。自分のアタマの悪さにガッカリ。
「レオノーラの卵」(日高トモキチ)
異世界を舞台にしたファンタジー。町の工場で働く若い娘・レオノーラが産んだ卵が男か女か賭けないか、というところから始まる。
この作品、他のアンソロジーでも読んだので、今回が再読。でも内容がよく分からない。
例えばレオノーラの働いている工場のことを「工場長の甥の叔父が工場長を務めていた工場」と記述してる。
よーく考えれば、最初の "工場長" と途中の "工場長" が別人の可能性もあるよなあ、って思えるのだが、とにかく全編がこんな感じで、読んでいてやたら疲れてしまい、ストーリーが全くアタマに入ってこない。うーん。
「人間ごっこ」(軒上泊)
売れない役者の岸川は劇団を辞めてしまうが、妻もまた彼を見限って家を出ていってしまう。9年後、場外馬券場の警備員をしていた岸川は、意外なところで妻と再会するが・・・
岸川の描き方が、もうこれ以上のダメ人間はなかなかいないのではないかと思わせる。そんな男が終盤に至って変貌する。ひとまずは物語にけりがつくけど、先は分からない。
岸川くんの「明日はどっちだ」(笑)。
「負けた馬がみな貰う」(法月綸太郎)
200万円の借金を抱えたフリーター・瀬川は高額報酬に惹かれて、ある心理実験にモニター参加する。それはギャンブル依存症治療プログラムの一種で、彼に課せられたミッションは「数週間から数ヶ月の間、競馬で負け続けること」。すなわち、毎日すべてのレースで "外れ馬券を買い続ける" ことだった・・・
ラストで "実験" の様相が一変するのも驚きだが、さらにひとひねり。これがまた現代ならではのオチ。
「死争の譜 ~天保の内訌~」(冲方丁)
ちなみに "内訌"(ないこう)とは内輪もめのこと。
江戸時代、碁所(ごどころ)という役職があった。寺社奉行の管轄の公職でもあり、当然ながら当代最高の碁打ちが就くものとされた。
その碁所の座を巡っての、名人たちの戦いが描かれる。表だったものだけでなく、水面下の暗闘めいたものまで含めて。
当時は将棋よりも囲碁のほうが格が上だったみたいで、碁所を巡って文字通り命を賭けた男たちの執念が凄まじい。
私は囲碁はできないが、将棋はちょっと知ってる。小学校の頃、覚えたばかりの将棋で父の知人と対戦したことがある。当然ハンデをもらい、相手は飛車角落としどころではない、王と歩だけしか持たなかった。それなのに、コテンパンに負けてしまったんだから・・・まあそれも今ではいい思い出だが(笑)。
思い起こせば、私自身は賭け事はほとんどしてこなかったなぁ。強いていえば、何年かにおきに、宝くじを買ってたことくらいかな。結果は、6000円分買って3600円当たったのが最高。当然ながら赤字だ。
まあ、私が自由に使える金は、みんな本と酒に注ぎ込んでるので、そもそもギャンブルに回せる資金が無いのだが(笑)。
アンソロジー 初恋 [読書・その他]
評価:★★★
女性作家集団「アミの会」によるアンソロジー。
"初恋" がテーマだが、甘酸っぱい話ばかりではない(というかほとんどない)。苦味も辛味も塩味も、ミステリからサスペンス、はてはホラーまで何でもあり。
「レモネード」(大崎梢)
亜弥(あや)は、20年ぶりに中学校時代の友人・リサと再会する。彼女は美人で、中学生の頃から男子には人気があった。
当時、亜弥はサッカー部の島村くんに片思い。しかし島村くんはリサに想いを寄せていた。そのリサが好きになった男子は、意外にも、さえない男子の中里くんだった・・・
"初恋は実らないもの" というが、"縁は異なもの" でもある、という話。
「アルテリーベ」(永嶋恵美)
定年退職後、妻の勧めでドイツ語教室に通い始めた原島悟。そこで隣の席になった女性と親しくなるが、彼女は妻の幼馴染みだった・・・
意表を突くラストを迎えるのだが、うーん、こういう初恋もあり得るよねぇ。
「再燃」(新津きよみ)
年の差のある夫に先立たれた "わたし" は、還暦同窓会に出席する。そこには初恋の相手だった向井も出席していた。そして後日、向井の方から「会いたい」と連絡が来たのだが・・・
人生百年時代だからね、こういうこともあるでしょう。しかしこの展開にはびっくり。
「触らないで」(篠田真由美)
語り手は古物商を営む女性。ある夜、店の方が騒がしい。そこには10歳にも満たない少女がいて、自分の身の上を語り出す。それと同時に体の方も成長を始める。
幼い頃から彫刻が好きだったが母には認められず、弟だけが理解者だったこと。才能を認めてくれた師のもとで創作に励んだこと。しかし兄弟子たちには、色仕掛けで師に取り入ったと責められたこと。彫刻家として自立するために師から離れようとしたこと・・・
芸術に掛ける情熱と男女の情念が複雑に絡み合うさまをホラータッチで描く。
「最初で最後の初恋」(矢崎在美)
留学することになった泰一は、幼馴染みで親友の悠矢に頼みごとをする。月に一度、祖母の千鶴子を訪ねてほしいと。頼まれた悠矢は、千鶴子とともにスイーツ巡りをしたり映画を観たり。そして彼女は、悠矢に今は亡き夫・源吾のことを語り出すのだが・・・
この千鶴子さんが、実に愛らしい。こんな女性と結婚できた源吾さんは幸せだ。
「黄昏飛行 涙の理由」(光原百合)
瀬戸内海に面した街・潮の道(しおのみち)。永瀬真尋(まひろ)は、地域FM放送のパーソナリティをしている。地元の寺・地福寺で開かれる、女性の幽霊画を集めた『隠れた名画展』に上司の局長と共に出かけるが、そこで局長が一枚の絵に見入ってしまう・・・
真尋と局長の会話がとにかく楽しい。どうやら真尋さんは局長に想いを寄せているみたい。続きがあったら読みたいものだ・・・と思ったのだけど、作者は昨年(2022年)の8月にお亡くなりになってる。この人の作品、好きだったんだけどね。残念です。合掌。
「カンジさん」(福田和代)
デイケア「やすらぎハウス」に通ってくる91歳の千代子は、亡き夫・カンジの思い出話を語る。しかし彼女の夫はカンジという名ではない。「カンジさん」は彼女の認知症の産物なのだ。
やがて千代子は亡くなるが、今度は別の女性が「亡き夫のカンジさん」の話をし始める・・・
ホラータッチのオチにちょっとゾクリ。
「再会」(柴田よしき)
中学生だった "私" は、受験塾で知り合ったコウちゃんに恋をした。横浜でデートもした。でもその後、2人は再会することはなかった。
そこから2つのエピソードを挟み、長い年月の末に2人はついに再会を果たすのだが・・・
なかなかミスリードが巧みで、最後のオチに持っていく。
「迷子」(松村比呂美)
35歳で未婚の智沙(ちさ)のもとに見合い話が持ち込まれる。相手は同年齢の男性・洋介。しかしバツイチで5歳の男の子がいる。悩んだ末、会うことにしたが、洋介の連れ子の佑樹を見て智沙は驚く。3ヶ月前、デパートで迷子になっているのを彼女が見つけて、面倒を見てあげた子だったのだ・・・
笑えて泣ける、"ちょっといい話"。このアンソロジーのトリを務めているのだが、最後にこの話があってよかった。ほっこりした気持ちで本が閉じられる。
タグ:ラブ・ストーリー
彼方のゴールド [読書・その他]
評価:★★★☆
まず書いておくが、私はスポーツが不得手だ。
不器用なので球技はからっきし。小学校の昔から、かけっこで上位に入ったためしがないくらい足も遅い。水泳は平泳ぎで25mプールを何とか泳ぎ切れるかどうかというレベル。辛うじてスキーは人並みくらいには滑れるかな。たいていのコースは何とか転ばずに降りてこられるから。とはいっても、もう15年くらい行ってない。
そのせいか、スポーツ中継にもあまり思い入れがない。オリンピックはそれなりに観るし、日本人がメダルを取れば嬉しいとは思うけど。
現在、甲子園では高校野球まっさかり。球児たちの熱闘ぶりには頭が下がるけど、その一方でいろいろな ”邪念” が湧いてきてしまうんだよねぇ・・・いや、 ”邪念” というと角が立つね。”素朴な疑問” としておきましょう。
その内容をここに書き出すと、熱烈な高校野球ファンから袋だたきにされてしまうだろうから、ナイショにしておきますが(笑)。
閑話休題。
本書は、そのスポーツをテーマにした小説だ。上に書いたように、スポーツに疎い私が、なんでこの本を読んだのか。
まあ、好きな作家さんの本だというのが大きいかな。その作家さんが、スポーツという題材をどんな風に描いたかも興味があったし。
本作は総合出版社・千石社を舞台にしたシリーズの4作目。とはいっても各作品は独立していて主人公も異なるので、本書から読み始めても全く問題ない。
主人公は入社3年目の目黒明日香。営業部から異動になった先は総合スポーツ雑誌「Gold」編集部。
ちなみに千石社のモデルは文藝春秋社(本書は文春文庫刊)。「Gold」のモデルは「Sports Graphic Number」だそうだ。
記者としては新米ながらも、明日香はバドミントン、プロ野球、マラソン、女子バスケット、Jリーグと、スポーツ選手たちへ取材し、記事に仕立て、誌面を通じて読者へ伝えていく。
読者は、一冊のスポーツ雑誌が完成するまでに、記者以外にも多くの ”その道のプロ” が関わってることを知ることになる。その一連の流れを追っていく ”お仕事小説” の面がある一方、明日香自身の物語も描かれていく。
小学校の頃、スイミングスクールに通っていた明日香。彼女自身にとっては習い事のひとつでしかなかったが、一緒に通う仲間には、選手コースに入って本格的に競泳に取り組んでいる者もいた。
彼ら彼女らが描く究極の夢はオリンピック出場、そして金メダルだ。
結果のタイムに泣き、笑い、喜び、悔しがり。選手たちの間には時に激しい軋轢まで生じる。それでも上を目指して諦めずに挑み続ける。しかしその一方で、競技から離れていく者もいる。その理由もまた様々。
物語の序盤では回想で綴られるのだが、中盤以降、明日香はそのときの仲間たちと再会していく。そして、意外な現在の姿も知ることに。
冒頭にも書いたように、私はスポーツというものにさほど思い入れのない人間なのだけど、「スポーツを伝える」ということの ”目的” というか ”意義” は分かったように思う。
明日香の視点から描かれる物語はとても興味深く、けっこう楽しく読ませてもらいました。
発現 [読書・その他]
評価:★★☆
大河ファンタジー『八咫烏』シリーズで有名な著者のノンシリーズ作品。今回はホラーだ。
平成30年。
主人公・村岡さつきは大学1年生。一回り年の離れた兄・大樹(だいき)とその妻・鞠香(まりか)との間には5歳の娘・あやねがいる。
ある日、彼女が通っている大学まであやねが訪ねてきた。両親がケンカをしたのだという。そしてその夜、大樹は妻子を置いて実家に戻ってきてしまう。
大樹は異様に憔悴していた。”ありえないもの” が見えるようになったのだという。精神科医の治療を受けても改善せず、性格も行動も一変してしまった兄を見ていたさつきは、かつて母が同じような状態になったことを思い出す・・・
昭和40年。
地方で農業を営む山田省吾のもとへ、東京で暮らす兄・清孝の訃報が届いた。
死因は自殺だった。立体交差橋の欄干を自ら乗り越えて、下の道路へ転落したのだという。
葬儀に参列した省吾は兄の様子を訊いて回る。仕事では優秀で人望もあり、家庭も円満。そんな兄が妻子を残して自ら命を絶つはずがない。
警察から得た情報によると、兄は死ぬ直前、泣いていたらしい。そして自ら欄干に上がり「彼女が、追いかけてきた」と言って身を投げたのだという。
かつて清孝と省吾の2人は揃って満州にいた。清孝は軍人として、省吾は開拓団の一員として。終戦後、清孝はシベリアに抑留され、省吾は清孝以外の家族全員を喪ったが、ともに九死に一生を得て帰国を果たしていた。
省吾は清孝が自殺した理由を調べようとするが、清孝の妻・京子はなぜかそれに反対し、兄が戦時中のことを記録したノートを燃やそうとするのだった・・・
物語は平成30年と昭和40年、二つの時代を交互に描いていく。もちろん終盤では一つにつながり、大樹の幻覚や清孝の自殺の理由もまた明らかになる。
私は怪談とかホラーというものが今ひとつ好きになれない。小野不由美の『悪霊』シリーズみたいに、けっこう楽しめるものもあるので、ホラー作品全部がダメというわけではないのだけど。
好き嫌いは多分に感覚的なもので、作品ごとに異なる。理由なんてあってないようなものなのだが、本書に関しては理由がハッキリしてるように思う。
以下の文章はネタバレに属することかと思うので、未読の方はご注意を。
本書の後半に入ると、ヒロインであるさつきにも兄と同じような ”幻覚” 症状が現れる。だが、彼女がそんな目にあわなければならない理由はないのだ。一言で言えば ”とばっちり” である。
さらに言えば、兄弟がこの ”幻覚” から解放される描写もない。つまりこの兄妹はこのあとの人生で、ずっと ”幻覚” を抱えていかなければならない。
本来責めを負う必要がない者にまで ”業” を背負わせる。これは理不尽としか言い様がない。
もし本当に祟りが存在するのなら、祟りを発生させるような悪行を為した者をきっちり呪い殺して、そこで終わりにするべきだと思うし、数十年後の無関係な人間にまで祟りを降らしたら、完全な ”八つ当たり” だよねぇ。そんな理不尽がまかり通る物語はやっぱり好きになれないんだなぁ。
ホラー好きな人からしたらトンデモナイ奴だと思われるかも知れないが、それが私の正直な感覚。
まあ本書においては、上記のような描写を通じて作者が訴えたいものがあるのは分かるし、それにはホラーという形式が効果的だと考えたのだろう。
でもね、やっぱりホラーは私の好みのジャンルではないと再確認しました。
ゴーストハント7 扉を開けて [読書・その他]
評価:★★★☆
主人公兼語り手は女子高生・谷山麻衣。彼女がアルバイトをしているのは心霊現象を専門に調査する「渋谷サイキックリサーチ」(SPR)。
そこの所長である美少年、通称ナルと個性的なゴーストバスターたちが繰り広げるホラーな冒険を描くシリーズ、第7巻目にして最終作。
前巻で、能登で老舗料亭を営む吉見家の事件を解決したSPR一行は、東京への帰路につくが、長野へ向かう山越えの途中で道に迷ってしまう。
今さらながらだが、本シリーズのもととなる『悪霊シリーズ』が書かれたのは1989~92年にかけて。改稿・改題された本シリーズも、作中に年代表記はないけれどおおむねこの時代の出来事のようだ。
作中に携帯電話は登場しないし、インターネットも登場しない。カーナビも、一般車にも搭載されるような低価格化が進んだのは93年以降みたい(ってwikiに書いてある)なので、本書でSPR一行が乗っている車にも装備されていないのだろう。作中でも、紙の地図を見てる描写があるし。
私自身を振り返っても、カーナビ付きの車を最初に買ったのは90年代末だったような記憶がある。
閑話休題。
一行が辿り着いたのは山中のダム湖。
そこで湖面を見つめていたナルは呟く。「やっと、見つけた・・・」
ナルは突然、SPRの解散を宣言し、湖畔のバンガローに滞在することを決める。さらには業者に連絡を入れて、湖にダイバーを投入することも。
戸惑う麻衣たちもとりあえず一緒に湖畔に残ることを決めるが、そこにダムの地元の町長が訪れ、SPRに調査を依頼してくる。
近くにある廃校となった小学校に幽霊が現れるのだという。サルベージの結果待ちだったナルは調査を引き受け、一行は現地へ向かう。
廃校になったのは5年前の5月。年度途中という半端な時期に廃校となったことからして曰くありげなのだが、調査が進むにつれて意外な事情が明らかになってくる。しかも一行は校舎の中に閉じ込められ、外に出ることができなくなってしまう・・・
廃校に潜む秘密と、それを解決していくSPRの活躍が描かれるのだが、最終作だけあって麻衣さんも大活躍する。
しかし本書は最終作であるから、真の目玉はシリーズの根底にあった謎が明らかになることだ。
「ナルはなぜ学校に行っていないのか?」
「彼の両親は何をしているのか?」
「SPRの開設資金/運営資金は誰が出しているのか?」
「彼が頻繁に日本中を巡って旅に出ていたのは、何のためだったのか?」
「そして、ナル自身の正体は?」
シリーズ読者からすれば、
「SPRは本当に解散してしまうのか?」
そして
「麻衣の思いはナルに通じるのか?」
あたりが気になるところかな(笑)。
原典となる『悪霊シリーズ』には、もう一冊だけ『悪夢の棲む家』という長編があるのだけど、こちらは改稿の対象にはなっていないみたい。
7冊もつき合ってくるとキャラたちにも親しみができてきて、できればまたSPRの御一行さんの掛け合い漫才みたいな会話劇を読みたい気もするのだけど、こればっかりは作者の胸三寸ですからねぇ・・・
アメリカ最後の実験 [読書・その他]
評価:★★★
主人公・櫻井脩(しゅう)はアメリカ西海岸にやってきた。目的は二つ。
ひとつめは、ジャズの名門〈グレッグ音楽院〉を受験するため。
もう一つは、7年前に渡米したまま消息を絶った父・俊一を捜すため。
音楽院は、風変わりな試験をしていた。
まずは街頭のあちこちに設置してあるピアノを飛び入りで演奏すること。観客の反応を含めて、有望と判断されれば次に進める。
そのようないくつかある予備試験を突破しなければ、学院内で行われる本試験に臨めないのだ。
試験を受けていくうちに、脩はスキンヘッドの巨漢マッシモやマフィアの御曹司と思われる少年ザカリーなど、他の受験生とも知り合っていく。
当然ながら彼ら以外の多くの受験生もいて、そのほとんどはどんどん淘汰されていく。
恩田陸の「蜜蜂と遠雷」みたいな雰囲気もちょっとあるが、毎回変わったシチュエーションでの試験といい、クセのある演奏課題や、用意された楽器にも ”罠” が隠されてたりと、マンガ的な描写も。
巻末の解説によると、作者も「格闘技マンガ」を念頭に置いて書いてたらしいし。
マッシモは俊一のことを知っていた。彼はアメリカ先住民の少女と暮らしながら演奏活動をしていたという。
俊一の弾いていたシンセザイザーは特別製のようで、〈パンドラ〉と呼ばれたその楽器は玄妙な響きを奏でていたという。
マッシモの伝手で、脩はその少女リューイ(7年後の今ではすでに少女ではないが)に会いにいく。
脩たちの物語と並行して、全米各地で謎の連続殺人事件が起こっていることが描かれている。やがて脩の身近にも犠牲者が現れて・・・
ミステリのようにもとれるかも知れないが、本書は本格ミステリではないので連続殺人を行っている真犯人がいるというわけではない。
全米各地で起こっている事件は、殺人衝動に駆られる人々が連続的にあちこちに現れているわけで、そのあたりはSFとして捉えるべきだろう。
もっとも、脩の身近で起こった殺人については終盤で犯人が明かされるので、まるっきりミステリではない、というわけでもないが・・・
音楽小説でありミステリでもありSFでもある。ジャンルを超えた要素をまとめて、ひとつのストーリーとして語りきっているのは流石に上手いとは思う。
そこそこ楽しんで読ませてもらったけれど、頻出する音楽用語(ジャズ用語?)は馴染みがないものが多い。物語を理解するには差し支えないかもしれないけど、ジャズやシンセサイザーに詳しい人ならもっと面白く読めるのだろうとも思った。
ちなみに文庫版の表紙には4人の人物が描かれているが、左からザカリー、脩、リューイ、マッシモ、だろうと思う。
メインとなるこの4人だけでなく、脇役として登場する者たちもキャラが立っていて印象に残る。